
織田信長と平手政秀の関係性
戦国時代の大名家に誕生した子供の生育環境は今とは違い、両親に変わって養育や教育を行う乳母や傅役という存在の家臣がいました。 織...

戦国時代の大名家に誕生した子供の生育環境は今とは違い、両親に変わって養育や教育を行う乳母や傅役という存在の家臣がいました。 織...

1543年に中国の貿易商人であった王直の船が種子島に漂着し、その船にポルトガル人が乗船していたことがきっかけとなり、南蛮貿易がはじまります。...

本能寺の変での織田信長を映像化した作品の多くに、「人生五十年、下天の 云々」と謡い舞う信長の姿が描かれ、能楽との関わりの深さを感じさせます。...

戦国時代の兵士は、江戸時代のような士農工商といった明確な身分制度がなく、農業に従事しながら戦さの時だけ駆り出される形態がとられています。 ...

岐阜駅前には、西洋甲冑に身を包み西洋兜を手にした金の織田信長公の像が作られており、戦国武将のなかでも、特異な服装をしていたことがわかります。...
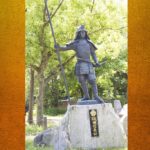
戦国時代の武将の多くが、元服するまでの幼名と元服後に用いた通称と実名をもつ者が多く、織田信長も多くの名前と官位をもっています。 ...

桶狭間の戦いで、今川義元の2万5000ともいわれる大軍を約10分の一の軍勢で撃破した織田信長は、戦国武将として全国区の存在となります。 ...
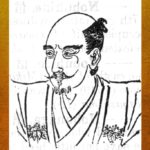
戦国時代の三英傑として名を連ねる織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三人ですが、信長の家臣が秀吉であり、信長と家康とは同盟関係、秀吉と家康は信長の...

織田信長には、桶狭間での少数の軍勢による大軍の撃破、長篠の戦いでの鉄砲隊による騎馬隊との戦い、石山本願寺に対する兵糧攻めなど、敵に合わせた戦...
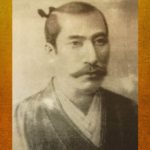
織田信長が天下統一を目指した戦国時代には、室町幕府と天皇という二大権威が存在しており、合理主義だった信長は、これらの権威を最大限に活用したと...